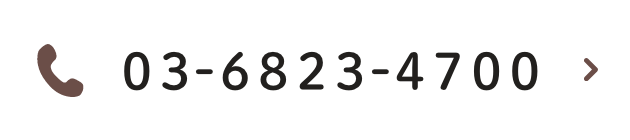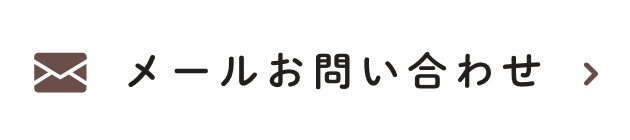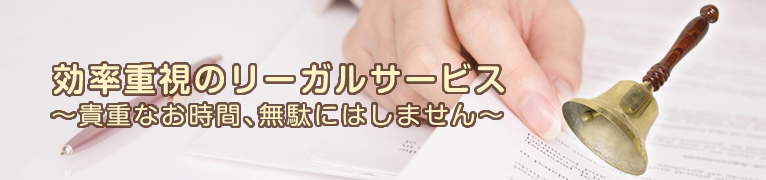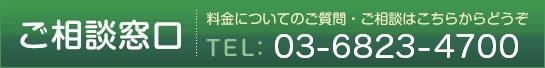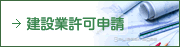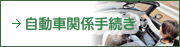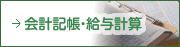相続・遺言
相続とは

相続とは死亡した人の財産が、その人と一定の身分関係にある人に移転することです。
死亡した人のことを「被相続人」といい、被相続人と一定の身分関係にある人のことを「相続人」といいます。相続によって移転する財産、は不動産や現金などの財産だけでなく、借金などの財産(負債)も含まれます。
相続人は、プラスの財産だけを相続してマイナスの財産は相続しないといったことはできません。資産と負債のバランスを確かめ、じっくりと相続方法を決める必要があります。
当事務所では、相続のご相談から遺言書の作成までを、ご依頼主様とともにじっくりと考えさせていただきます。
相続の手続きについて
遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。
遺言がある場合、遺産は原則として遺言で指定されたとおりに分割されます。
ですから、相続人と受遺者の間の遺産分割についての話し合いは不要となります。
遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に無効な場合には、民法の規定により、
相続人になれる人の範囲と順位が決まります。
そして、この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」と言います。
法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
法定相続分について
遺言書がない場合、民法は誰が相続人となるのかを規定していますが、各相続人が受け継げる相続分についても規定しています。それを法定相続分といいます。
- 子と配偶者が相続人の場合
- 子が2分の1、配偶者が2分の1。
- ※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
- 父母と配偶者が相続人の場合
- 配偶者が3分の2、父母が3分の1。
- ※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
- 兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
- 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
- ※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。
法定相続人の範囲
民法の規定により法定相続人になれる人は以下の4種類の立場の人です。
1.配偶者(法律上の夫または妻)
2.子(直系卑属)
3.父母(直系尊属)
4.兄弟姉妹(傍系血族)
遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろんですが、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。仮に内縁の妻や長男の嫁、叔父、叔母などに遺産を残したいと考えているならば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
費用
※税込
| 遺言執行/相続手続き一切 | 資産額2,000万円以下 | 330,000円 |
|---|---|---|
| 資産額2,000万円超 | 資産額の1.575% |
遺言執行/相続手続一切に含まれるもの
- 遺産分割協議書作成パックの内容全て
- 被相続人関連の各種名義変更手続サポート
- 被相続人死亡から発生する手続のサポート
- 遺産分割案の提示(遺言のないとき)
- 遺産分割協議立会い
- 司法書士による不動産名義変更手続
- 相続税の基礎控除を超える可能性があるものについては、
税理士による節税アドバイス及び税務申告 - 弁護士等の紹介
注意
*戸籍謄本、住民票等の請求に係る官公署手数料、登録免許税、交通費、郵送料などの実費は別途必要です。
*相続人の印鑑証明書は各相続人様がご用意ください。
遺言書の作成

自分の死後のことを考えたことがありますか?
「財産の事で家族の人間関係に亀裂をいれたくはない。」と考えるのは当然ですよね?
そこで、自分のいない現実世界では、
必ず遺言書が必要となってきます。
ただ、実際には遺言を書いたからすべてが自由に処分できるわけではありません。
「遺留分」を侵さないという限度で、自分の財産、身分に関する事項について死後に意思表示ができます。自分の財産を自由に活かすために、また、残された家族に無用な問題を持ち込まないためにも、今のうちに遺言に対する理解を深め、遺言書を作成することをお勧めします。
遺留分
兄弟姉妹、甥、姪を除いた法定相続人が最低限、相続を保証された相続権利のことです。
原則は「法定相続分の半分×法定相続分」とされています。
相続人が遺言者の父母のみの場合だけ「法定相続分の1/3×法定相続分」と決まっています。
遺言書の種類
1. 自筆証書遺言(全文自筆で証人がいりません。)
2. 公正証書遺言(公証人が口述筆記で作成。証人が2人以上必要。)
3. 秘密証書遺言(本人、または代筆、ワープロで作成。公証人1人、証人1人以上必要。)
遺言書作成にかかる費用
※税込
| 遺言書作成 | 自筆証書遺言(文案作成と指導) | 44,000円~ |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 (文案作成、指導、戸籍・登記簿等収集、公証役場立会い) |
110,000円~ | |
| 秘密証書遺言 (文案作成、指導、公証役場立会い) |
66,000円~ |
遺言書作成に含まれるもの
- 希望内容を十分に聴取の上、アドバイスを加え、文案を作成
- ご納得いただくまで修正を実施
- 公正証書遺言及び秘密証書遺言については、証人日当
注意
*公証人手数料、各種証明書類等実費は別途
遺産分割協議が必要な場合
※税込
| 遺産分割協議書作成パック | *複雑な案件については相続手続一切で対応いたします | 44,000円~ |
|---|
遺産分割協議書作成パックに含まれるもの
- 財産調査→財産目録作成、相続人調査(相続関連の戸籍・住民票取得)
→相続関係説明図作成 - 遺産分割協議書作成
- 相続相談、司法書士、税理士他の専門家の紹介
注意
*戸籍謄本、住民票等の請求に係る官公署手数料、登録免許税、交通費、郵送料などの
実費は別途必要です。
*相続人の印鑑証明書は各相続人様がご用意ください。
※税込
| 遺産分割 協議書のみ |
遺産分割協議書作成と製本まで | 55,000円~ |
|---|---|---|
| 遺産分割協議書作成のみ (添付メールによる納品) |
インターネット特価! 33,000円~ |
相続に関する調査
※税込
| 戸籍・相続人調査 | *複雑な案件については別途協議 | 55,000円~ |
|---|---|---|
| 相続財産調査 | *複雑な案件については別途協議 | 55,000円~ |